「あれ?計算が合わない…」
電気・電子回路、特に高周波を扱う伝送線路で、こんな経験はありませんか?
「75Ωのシステムなのに、50Ωの測定器を使ったら、なんだか予想と違う値が出た…」
今回は、まさにそんな具体的な疑問を解決します。具体的には、「75Ω系の伝送線路の出力を、50Ω系の電力計で測定したら12.8mWだった。この時、電力計の端子電圧は0.8Vになる。そして、元の信号源の開放端子電圧は2Vである」という状況設定の裏側にある物理法則と計算プロセスを、ステップ・バイ・ステップで徹底解説します。
さらに応用編として、増幅器のような能動素子において、その開放出力電圧と整合負荷時の出力電力の関係がどのように決まるのかについても解説します。
この記事を読めば、あなたもインピーダンスが異なる機器を接続した際の挙動や、増幅器の基本的な出力特性を理解し、測定値の謎を解き明かせるようになるでしょう!
この記事の概要
- 問題の核心: なぜインピーダンスが違うと測定結果が変わるのか?
- 基本の理解: インピーダンスとは?整合・不整合が意味すること。
- 重要公式: 電力計算と電圧分割の法則をわかりやすく解説。
- ステップ解説: 実際の数値(12.8mW, 0.8V, 2V, 75Ω, 50Ω)を使って計算プロセスを追体験。
- 応用編: 増幅器の開放出力電圧 E と整合負荷時の出力電力 Pout の関係式 (
E = sqrt(Pout × 4 × 50 Ω)) の導出。 - 結論: なぜこの状況で全ての数値がピッタリ合うのか、その理由を解明。
まずは基本から!インピーダンスって何?
回路の話をするとき、「抵抗」はお馴染みですよね。電流の流れにくさを表します。しかし、交流回路、特に伝送線路のような高周波を扱う場合、「インピーダンス (Z)」という考え方が不可欠になります。
- インピーダンス (Z): 交流回路における「電流の流れにくさ」を表します。抵抗(R)だけでなく、コイルによる誘導性リアクタンス(XL)やコンデンサによる容量性リアクタンス(XC)も考慮した、より広範な概念です。単位は抵抗と同じオーム(Ω)です。
- 特性インピーダンス (Z0): 伝送線路(同軸ケーブルなど)が持つ固有のインピーダンス。線路の材質や形状で決まります。今回の例では
Z0 = 75 Ωです。 - 信号源インピーダンス (ZS): 信号を送り出す側の機器(信号発生器など)が持つ内部的なインピーダンス。後述する増幅器では出力インピーダンス (Zout) とも呼ばれます。
- 負荷インピーダンス (ZL): 信号を受け取る側の機器(アンテナ、測定器など)のインピーダンス。今回の例では電力計が負荷であり、
ZL = 50 Ωです。
インピーダンス整合と不整合
伝送線路で効率よく信号(電力)を伝えるためには、インピーダンス整合が非常に重要です。
- 整合 (Matching): 信号源インピーダンス (ZS)、伝送線路の特性インピーダンス (Z0)、負荷インピーダンス (ZL) がすべて等しい状態 (
ZS = Z0 = ZL)。このとき、信号は反射することなく、効率的に負荷に伝わります。(※注:最大電力伝送の条件は厳密にはZL = ZS*(共役整合)ですが、ここでは抵抗性インピーダンスを主に考えます) - 不整合 (Mismatch): これらのインピーダンスが異なる場合。接続点で信号の一部が反射してしまい、信号源側に戻ってしまいます。これにより、負荷に伝わる電力が減少したり、定在波が発生して予期せぬ電圧・電流分布になったりします。
今回のケース (Z0=75Ω, ZL=50Ω) は、まさにインピーダンス不整合の状況です。
問題設定の再確認:何がわかっていて、何を知りたいのか?
ここで、今回の具体的なシナリオを整理しましょう。
- 伝送線路: 特性インピーダンス
Z0 = 75 Ω - 信号源: 開放端子電圧
VOC = 2 V、 内部インピーダンスZS = 75 Ω(※後述しますが、信号源は75Ωの線路に整合していると仮定するのが最も自然です) - 負荷: 電力計。入力インピーダンス
ZL = 50 Ω - 測定結果: 電力計で測定された電力
PL = 12.8 mW
|
|
私たちが確認したいのは、これらの数値が物理法則に則って、矛盾なく成り立っていることです。
計算ステップ①:測定電力から負荷の端子電圧を求める
まず、電力計で測定された電力 PL = 12.8 mW と、電力計のインピーダンス ZL = 50 Ω から、実際に電力計にかかっている電圧(端子電圧 VL)を計算します。
電力 P、電圧 V、抵抗(インピーダンス) R の関係式は P = V2 / R です。これを V について解くと、V = sqrt(P × R) となります。
これを使って VL を計算すると:
VL = sqrt((12.8 × 10-3 W) × (50 Ω))
VL = sqrt(0.64 V2)
VL = 0.8 V
これは、ご提示の情報通り、電力計の端子には 0.8V の電圧がかかっていることを示します。
計算ステップ②:開放端子電圧から負荷の端子電圧を求める(電圧分割)
次に、信号源の開放端子電圧 VOC から、負荷にかかる端子電圧 VL を求める計算を見てみましょう。ここで「電圧分割の法則」を使います。
信号源(VOC, ZS)と負荷(ZL)が直接接続されている(または伝送線路の影響を等価回路上で考慮した)場合、負荷にかかる電圧 VL は以下の式で表されます。
【ここがポイント!】 なぜ ZS = 75 Ω と仮定するのか?
問題設定では「75Ω系の伝送線路」とあり、信号源についての明示はありませんでした。しかし、一般的に信号源はその伝送システム(ここでは75Ω系)に整合するように設計されます。つまり、ZS = Z0 = 75 Ω と考えるのが最も自然で、工学的な慣例にも沿っています。この仮定のもとで計算を進めます。
では、実際に値を代入してみましょう。
VOC = 2 V(与えられた情報)ZS = 75 Ω(上記の仮定)ZL = 50 Ω(電力計の仕様)
VL = 2 V × (50 / 125)
VL = 2 V × 0.4
VL = 0.8 V
驚きましたか? 計算ステップ①で電力測定値から求めた負荷の端子電圧と、完全に一致しました!
応用編:増幅器の開放出力電圧と整合負荷電力の関係
ここまでは、信号源を単純な電圧源と内部インピーダンスで考えました。次に、応用として増幅器の出力について考えてみましょう。増幅器も信号源の一種であり、その出力特性を知ることは重要です。
特によく議論されるのが、増幅器の開放出力電圧 E と、その増幅器に整合負荷を接続したときに負荷で消費される電力(出力電力 Pout)の関係です。
ステップ解説:開放出力電圧 E と整合負荷電力 Pout の関係
-
増幅器の出力側等価回路(テブナンの定理)
増幅器の出力側は、理想的な電圧源 E(これが求める開放出力電圧)と、その内部抵抗である出力インピーダンス Zout が直列に接続された等価回路(テブナン等価回路)で考えることができます。多くの高周波増幅器では、出力インピーダンスはZout = 50 Ωとされています。 -
整合負荷接続時の電圧分割 – なぜ VL = E/2 になるのか?
次に、この増幅器の出力端子間に、出力インピーダンスと等しい整合負荷 ZL を接続します。つまり、ZL = Zout = 50 Ωを接続する状況を考えます。
この回路では、増幅器の内部にある電圧源 E から見ると、内部の出力インピーダンス Zout と、外部に接続した負荷インピーダンス ZL が直列に接続されています。
回路に流れる電流 I は、オームの法則からI = E / (Zout + ZL)となります。そして、負荷 ZL の両端にかかる電圧 VL は、再びオームの法則からVL = I × ZLです。
これらを組み合わせると、負荷にかかる電圧 VL は次のように表せます。これが電圧分割の法則です。VL = E × (ZL / (Zout + ZL))ここで、整合条件である
ZL = Zoutを代入します。(今回の例ではZL = Zout = 50 Ω)VL = E × (Zout / (Zout + Zout))
VL = E × (Zout / (2 × Zout))分母と分子にある Zout が打ち消し合うため、
VL = E × (1 / 2) = E / 2これが、整合負荷を接続したときの負荷電圧 VL が、開放出力電圧 E のちょうど半分になる理由です。 電圧源 E の電圧が、全く同じ値を持つ内部インピーダンス Zout と負荷インピーダンス ZL に等しく半分ずつかかる(分圧される)ためです。この
VL = E / 2という関係は、整合条件における非常に重要な性質です。 -
整合負荷での消費電力 Pout
整合負荷ZL = 50 Ωで消費される電力 Pout(これが当初の式中の P に相当)は、負荷にかかる電圧 VL と負荷抵抗 ZL を使って次のように表せます。Pout = VL2 / ZL値を代入すると、
Pout = VL2 / 50 Ω -
開放出力電圧 E と出力電力 Pout の関係
ステップ2で導いたVL = E / 2(整合時の負荷電圧は開放電圧の半分)の関係を、ステップ3の電力の式に代入します。Pout = (E / 2)2 / 50 Ω
Pout = (E2 / 4) / 50 Ω
Pout = E2 / (4 × 50 Ω)この式を E2 について解くと、
E2 = Pout × 4 × 50 Ω最後に、両辺の平方根をとると、目的の関係式が得られます。
E = sqrt(Pout × 4 × 50 Ω)
補足情報について
- 電力利得 40 dB: これは入力電力 Pin と整合負荷時の出力電力 Pout の比率 (
Pout / Pin = 10(40/10) = 10000) を示します。もし入力電力が分かれば、出力電力 Pout を計算できますが、開放出力電圧 E と出力電力 Pout の関係式を導くだけなら、電力利得の値は直接使いません。 - 電源の内部インピーダンス 50Ω: これは増幅器の入力側が整合されていることを意味し、増幅器が最大の電力利得を得るための条件です。これも E と Pout の関係式そのものには直接影響しませんが、整合負荷時の出力電力 Pout が、所定の電力利得(40 dB)に基づいた値であることを保証する条件となります。
これまでの議論と同様に、信号源の特性(開放端子電圧、内部インピーダンス)と負荷インピーダンスの関係が、実際の電圧や電力を決定づける鍵となります。
結論:なぜこれで全てが繋がるのか?
今回の計算結果が示したことは、以下の通りです。
【伝送線路の例】
開放端子電圧2Vで内部インピーダンス75Ωの信号源 (VOC=2V, ZS=75Ω) が、インピーダンス50Ωの負荷 (ZL=50Ω) に接続された場合、負荷にかかる電圧(端子電圧)は電圧分割の法則により正確に0.8V (VL=0.8V) になる。そして、その0.8Vの電圧が50Ωの負荷にかかったときに消費される電力は、PL = VL2 / ZL の法則により正確に12.8mW (PL=12.8mW) となる。
【増幅器の例】
出力インピーダンスが50Ωの増幅器 (Zout=50Ω) において、整合負荷(50Ω)を接続したときに得られる出力電力を Pout とすると、その増幅器の開放出力電圧 E は、E = sqrt(Pout × 4 × 50 Ω) という関係で結ばれる。これは、整合接続時に負荷にかかる電圧 VL が開放出力電圧 E の半分 (VL=E/2) になることから導かれる。
どちらの例も、一見複雑に見える状況も、
- 信号源の特性 (VOC or E, ZS or Zout) を正しく設定(仮定)し、
- 負荷の特性 (ZL) を理解し、
- 物理法則(電圧分割、電力計算) を適用すれば、
測定結果や各パラメータ間の関係性が完全に説明できるのです。
インピーダンスの整合・不整合を理解することが、電気回路、特に高周波回路や伝送線路を扱う上で非常に重要であることがわかりますね。
重要なポイント(まとめ)
- 交流回路、特に伝送線路ではインピーダンスが重要。
- 信号源(ZS/Zout)、線路(Z0)、負荷(ZL)のインピーダンスが異なると不整合となり、信号の反射などが起こる。
- 負荷にかかる実際の電圧(端子電圧 VL)は、信号源の開放端子電圧 VOC (または E) と、ZS/Zout, ZL を用いた電圧分割の法則で決まる (
VL = VOC × ZL / (ZS + ZL))。 - 電力測定値 (PL) からも端子電圧 (VL) は計算できる (
VL = sqrt(PL × ZL))。 - 整合負荷時の出力電力 Pout と開放出力電圧 E の間には、
E = sqrt(Pout × 4 × Zout)という関係がある(Zout=50Ω ならE = sqrt(Pout × 4 × 50 Ω))。 - インピーダンスの整合性を考慮することが、正確な測定や効率的な信号伝送の鍵となる。
FAQ(よくある質問)
- Q1: 信号源インピーダンス (ZS) がもし50Ωだったら?(伝送線路の例で)
- A1: その場合、
VL = VOC × (50 / (50 + 50)) = VOC / 2となります。もしVOC=2VならVL=1Vとなり、電力はPL = (1V)2 / 50Ω = 20mWとなるはずです。記事中の測定値(12.8mW)とは異なります。
- A1: その場合、
- Q2: もし電力計も75Ωだったら? (伝送線路の例で整合していたら?)
- A2:
ZS=75Ω,ZL=75Ωなので、VL = VOC × (75 / (75 + 75)) = VOC / 2となります。VOC=2Vなら、VL=1Vです。電力はPL = (1V)2 / 75Ω ≈ 13.3mWとなります。
- A2:
- Q3: 開放端子電圧と端子電圧、結局どう違う?
- A3: 開放端子電圧 (VOC or E) は、信号源に何も負荷を接続していない、いわば信号源が「素」の状態で持っている最大電圧ポテンシャルです。端子電圧 (VL) は、実際に負荷を接続したときに、その負荷の両端にかかる電圧です。負荷を接続すると信号源の内部インピーダンス(ZS/Zout)と負荷インピーダンス(ZL)で電圧が分割されるため、通常 VL は VOC (または E) より小さくなります。
- Q4: 増幅器の例で出てきた「電力利得 40dB」や「電源の内部インピーダンス 50Ω」は、式の導出に関係ないの?
- A4:
E = sqrt(Pout × 4 × 50 Ω)という関係式そのものを導出する上では直接使いません。しかし、これらは実際にその増幅器が整合負荷時に Pout という電力を出力するための条件や背景を示しています。「電源の内部インピーダンス 50Ω」は増幅器の入力側が整合されていることを示し、「電力利得 40dB」はその整合条件下で入力電力(Pin)に対して出力電力(Pout)がどれだけ増幅されるか (Pout = 10000 × Pin) を示します。つまり、Pout の値が決まる背景にはこれらの条件が関わっています。
- A4:
この記事が、伝送線路や増幅器におけるインピーダンスと測定値の関係についての理解を深める一助となれば幸いです。電気の世界は奥が深いですが、一つ一つ法則を理解していけば、必ず道は開けます!
たび友|サイトマップ
関連webアプリ
たび友|サイトマップ:https://tabui-tomo.com/sitemap
索友:https://kentomo.tabui-tomo.com
ピー友:https://pdftomo.tabui-tomo.com
パス友:https://passtomo.tabui-tomo.com
クリプ友:https://cryptomo.tabui-tomo.com
進数友:https://shinsutomo.tabui-tomo.com

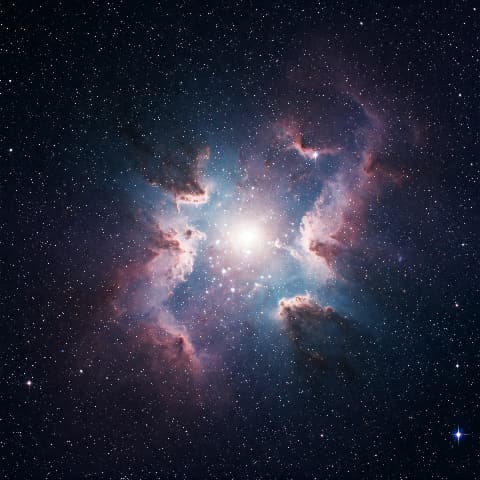
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=20879188&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0982%2F9784864810982_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=18830132&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2064%2F9784621302064.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

