「方向性結合器に100W入れたら、結合分を引いて99.99Wが出力されるはず…?でも、計算すると違うらしい…?」
前回、そんな疑問を持たれたかもしれませんね。高周波回路、特に方向性結合器の電力計算は、一見すると直感的でない部分があり、戸惑うことも少なくありません。しかし、ご安心ください!この記事を読めば、方向性結合器がどのように動作し、なぜあなたの計算と最終的な答えが少し異なるのか、その理由が明確にわかります。
プロのブロガーであり、この分野の専門家として、今回は方向性結合器の基本原理から、具体的な電力計算のステップ、そして多くの人がつまずきやすい「反射」の影響まで、例を交えながら徹底的に、そしてどこよりも分かりやすく解説します。もう「なんとなく」で済ませるのは終わりにしましょう!
- 方向性結合器って、そもそも何?どんな仕組み?
- 「結合度40dB」とか「反射係数0.05」ってどういう意味?
- 100W入力 → 結合10mW → 通過99.99W → 反射 → 最終出力99.74W の計算ステップ全解説
- なぜ単純な引き算「100W – 10mW」ではダメなのか?
- 方向性結合器の実際の使われ方
さあ、一緒に方向性結合器の奥深い世界を探求し、電力計算の「?」を「!」に変えましょう!
そもそも方向性結合器とは?初心者にもわかる基本
方向性結合器(Directional Coupler)は、高周波回路における一種の「信号の分岐点」のようなものです。主な役割は、メインの信号経路(主線路)を流れる電力の一部を、信号の流れを大きく乱すことなく「つまみ食い」して取り出す(結合させる) ことです。
方向性結合器のイメージ:信号の高速道路の検問所
まるで高速道路を走る車の流れ(信号電力)を止めずに、料金所や検問所(方向性結合器)で一部の車だけを別の出口(結合ポート)に誘導するようなイメージです。これにより、本線の交通(主信号)に大きな影響を与えずに、通過する交通量(電力レベル)を監視したり、一部を別の目的(測定や信号注入など)に利用したりできます。
4つのポート(出入り口)の役割
方向性結合器には通常、4つのポート(端子、出入り口)があります。
- 入力ポート (Port 1): 主な信号電力を入力する場所。
- 通過ポート (Port 2 / Through Port): 入力された電力の大部分が、ここを通過して出力される場所。主線路の「出口」。
- 結合ポート (Port 3 / Coupled Port): 入力電力の一部が「つまみ食い」されて出てくる場所。取り出される電力の割合は「結合度」で決まります。
- アイソレーションポート (Port 4 / Isolated Port): 理想的には、ここには電力が出てこない場所。通過ポート側からの反射波などが現れることがあるため、通常は終端抵抗(ダミーロード)で終端されます。
方向性結合器はなぜ「方向性」を持つのか?動作原理を徹底解説
方向性結合器がただの分岐器と違うのは、その名の通り「方向性」を持つ点です。つまり、入力ポートから入った電力が進む方向(順方向)に対してだけ、結合ポートに電力を取り出す ことができるのです。もし信号が逆方向(通過ポートから入力ポートへ)に進む場合、理想的には結合ポートには電力は現れません。この「方向性」はどのようにして実現されるのでしょうか?
主線路と副線路:電力伝送の二つの道
方向性結合器の内部には、メインの信号が通る「主線路」と、それに近接して配置された「副線路」という二つの伝送路があります。
電磁界の結合:見えない力でエネルギーを伝える
主線路を高周波信号が伝わると、その周りには電磁界(電場と磁場)が発生します。この電磁界が、すぐ隣にある副線路にも影響を与え、副線路内にも信号(電力)を誘起します。これが「結合」の基本的な仕組みです。まるで、隣を走るトラックの風圧で、自分の車が少し影響を受けるようなイメージです。
位相のキャンセル:アイソレーションの秘密
ここが「方向性」を生み出す重要なポイントです。副線路上に誘起される信号は、実は二つの経路(例えば、電界による結合と磁界による結合、あるいは構造に応じた複数の結合点) を通じて生成され、それらが合成されます。
- 順方向の信号に対して: 副線路を進む二つの信号は、うまく位相が揃って強め合い、結合ポートに向かいます。
- 逆方向の信号(主線路を逆走する信号や、通過ポートからの反射波)に対して: 副線路を進む二つの信号は、位相が互いに逆になり打ち消し合います。その結果、アイソレーションポートに向かう波はキャンセルされ、結合ポートにはほとんど電力が出てこなくなります。
これが、方向性結合器が特定の方向の信号だけを選択的に結合できる理由です。
4つのポートの役割(原理からのまとめ)
- 入力ポート: 信号が入る。
- 通過ポート: 信号の大部分がそのまま通過する。
- 結合ポート: 入力ポートからの順方向信号の一部だけが、位相が揃って取り出される。
- アイソレーションポート: 逆方向の信号や反射波は、位相キャンセルによってここに向かう(そして終端抵抗で吸収される)。
【本題】100W入力、40dB結合器、反射係数0.05… なぜ出力は99.74W?
さて、いよいよ本題の計算です。前回の疑問「入力100W、結合度40dB、出力に反射係数0.05のアンテナ接続」の状況を、ステップ・バイ・ステップで見ていきましょう。
問題設定のおさらい:
- 入力電力 (
Pin): 100 W (Port 1 へ) - 方向性結合器の結合度 (
C): 40 dB - 各ポートの特性インピーダンス (
Z0): 50 Ω (整合されている前提) - 通過ポート (Port 2) に接続された負荷: アンテナ(電圧反射係数
ΓL = 0.05)
なぜ「デシベル(dB)」を使うの?
計算に入る前に、少し寄り道です。「40dB」のように、高周波の世界では「デシベル(dB)」という単位がよく使われます。なぜでしょうか?
- 大きな範囲の数値を扱いやすくするため: 電力は時に非常に大きい値から小さい値まで変化します(例: 100W と 10mW)。dBを使うと、これらの比率を対数で表現するため、桁数を抑えて比較しやすくなります。10000倍は40dB、100倍は20dB、10倍は10dB、2倍は約3dBです。身近な例では音の大きさ(音圧レベル)もdBで表されますね。
- 掛け算を足し算にできる: 複数の機器を通る際の全体の利得や損失を、各部分のdB値を足し引きするだけで計算できるため、計算が簡単になります。
電力比のdB計算は 10 × log10(P2 / P1) です。
STEP 1: 結合ポート(Port 3)に出てくる電力(Pcpl)は? – 40dBの意味
結合度40dBとは、「入力電力に対して、結合ポートに出てくる電力の比が 10(40/10) = 10000 分の1」であることを意味します。
Pcpl = 100 W / 10(40/10)
Pcpl = 100 W / 10000
Pcpl = 0.01 W = 10 mW
まず、入力された100Wのうち、10mW が結合ポートに「つまみ食い」されることがわかりました。
STEP 2: 通過ポート(Port 2)へ「向かう」電力(Pthru_inc)は? – 損失を引く
入力された電力 Pin は、主に結合ポート Pcpl と通過ポート Pthru_inc に分配されます(ここでは、方向性結合器自体のわずかな内部損失(挿入損失)は無視できる理想的なケースを考えます)。
したがって、通過ポート (Port 2) に向かって進む(入射する) 電力は、入力電力から結合ポートに出ていく電力を引いたものになります。
Pthru_inc = 100 W – 0.01 W
Pthru_inc = 99.99 W
STEP 3: アンテナでの「反射」を考える – 反射係数0.05とは?
通過ポート (Port 2) の先には、アンテナが接続されています。このアンテナは完全に理想的な負荷ではなく、「電圧反射係数 ΓL = 0.05」という特性を持っています。
反射係数(Γ)とは?
- 接続点(ここではアンテナの入力部分)で、信号がどれだけ「跳ね返されるか」を示す指標です。
Γ = 0: 全く反射がない完璧な状態(インピーダンスが完全に整合している)。電力はすべて負荷に吸収されます。Γ = 1(絶対値): 全ての電力が反射される状態(全反射)。電力は全く負荷に吸収されません。0 < |Γ| < 1: 一部が反射され、残りが負荷に吸収される状態。
今回の ΓL = 0.05 というのは、電圧の振幅で5%が反射されることを意味します。これは非常に反射が少ない、良好な整合状態を示しています。
重要なのは電力反射係数
電力の計算をするためには、電力反射係数 |ΓL|2 を使います。
これは、アンテナに向かってきた電力のうち、0.25% が反射されて戻ってくる、ということを意味します。
STEP 4: 反射で失われる電力(Prefl)は?
アンテナで反射される電力は、アンテナに向かう電力 Pthru_inc に電力反射係数 |ΓL|2 を掛けて計算します。
Prefl = 99.99 W × 0.0025
Prefl ≈ 0.249975 W ≈ 0.25 W
アンテナに向かった99.99Wのうち、約 0.25W がアンテナで跳ね返されてしまうわけです。
STEP 5: 最終的にアンテナに供給される電力(真の出力 Pout)は?
アンテナが実際に消費(または放射)できる電力、つまり「真の出力電力」は、アンテナに向かった電力 Pthru_inc から、反射された電力 Prefl を引いたものです。
Pout = 99.99 W – 0.25 W
Pout = 99.74 W
あるいは、次のように計算することもできます。
Pout = 99.99 W × (1 – 0.0025)
Pout = 99.99 W × 0.9975
Pout ≈ 99.740025 W ≈ 99.74 W
これで、最終的にアンテナに供給される電力が約99.74Wとなる計算の全貌が明らかになりました!
「99.99Wが出力」という考え方のポイントと注意点
今回の計算で、なぜ最初の疑問にあった「99.99W」が最終的な答えではなかったのか、明確になったと思います。ここで重要なポイントを整理しましょう。
入射電力 vs 供給電力:言葉の定義が重要
- 入射電力 (Incident Power): ある点(今回はアンテナの接続点)に向かって進んでくる電力。STEP 2で計算した 99.99W はこれにあたります。
- 反射電力 (Reflected Power): 接続点で整合が取れていないために跳ね返ってくる電力。STEP 4で計算した 0.25W です。
- 供給電力 (Delivered Power / Absorbed Power): 実際に負荷(今回はアンテナ)に吸収され、消費(または放射)される電力。入射電力から反射電力を引いたもので、STEP 5で計算した 99.74W がこれです。「出力電力」という場合、通常はこの供給電力を指します。
つまり、「100W – 10mW = 99.99W」という計算は、アンテナでの反射を考慮に入れる前の「アンテナへの入射電力」 を求めたものだった、ということです。
理想的なモデルと現実:挿入損失の影響
今回の計算では、方向性結合器自体の損失(入力ポートから通過ポートへ抜ける際のわずかな電力ロス:挿入損失)をゼロと仮定しました。実際の方向性結合器には、わずかながら挿入損失(例えば0.1dBとか0.2dBとか)が存在します。もしこの挿入損失も考慮に入れると、通過ポートへ向かう電力(Pthru_inc)は99.99Wよりもさらにわずかに減少し、最終的な出力電力も99.74Wより少しだけ小さくなります。
方向性結合器って何に使われるの? 具体的な用途例
方向性結合器は、その特性を活かして様々な場面で活躍しています。
- 電力モニタリング: 送信機の出力電力が規定通りか、アンテナへ向かう電力を監視する。結合ポートから取り出した微小電力で測定できるため、主信号を妨げません。
- VSWR測定 / 反射測定: アンテナなどの負荷がどれだけ整合しているか(反射が少ないか)を測定する。順方向の電力と反射してくる電力を比較することでVSWR(電圧定在波比)を算出できます。
- 信号発生器のALC (Automatic Level Control): 出力レベルを一定に保つために、出力の一部を結合器で取り出し、それをフィードバックしてレベルを制御する。
- 信号注入: 既存の信号ラインに、別の信号(テスト信号など)を注入する。
まとめ:方向性結合器の電力計算をマスターしよう!
今回は、方向性結合器を使った電力計算、特に反射がある場合の考え方について詳しく解説しました。
重要なポイントのおさらい:
- 方向性結合器は、主線路の電力の一部を方向性を持って結合ポートに取り出すデバイス。
- 結合度 (dB) は、入力電力に対する結合電力の比率を対数で示す。dBから実際の電力比に変換して計算する (
10(dB/10))。 - 通過ポートへ「向かう電力(入射電力)」は、入力電力から結合電力を引いたもの(理想的な場合)。
- 負荷(アンテナなど)に反射係数があると、入射電力の一部が反射される。
- 実際に負荷に供給される電力(出力電力)は、入射電力から反射電力を引いたもの (
Pout = Pinc (1 - |Γ|2))。
これで、方向性結合器が関わる電力計算も、自信を持って取り組めるようになったのではないでしょうか。高周波の世界は奥が深いですが、一つ一つの原理と計算ステップを理解していけば、決して難解ではありません。
この記事が、あなたの疑問解消と理解の一助となれば幸いです!
たび友|サイトマップ
関連webアプリ
たび友|サイトマップ:https://tabui-tomo.com/sitemap
索友:https://kentomo.tabui-tomo.com
ピー友:https://pdftomo.tabui-tomo.com
パス友:https://passtomo.tabui-tomo.com
クリプ友:https://cryptomo.tabui-tomo.com

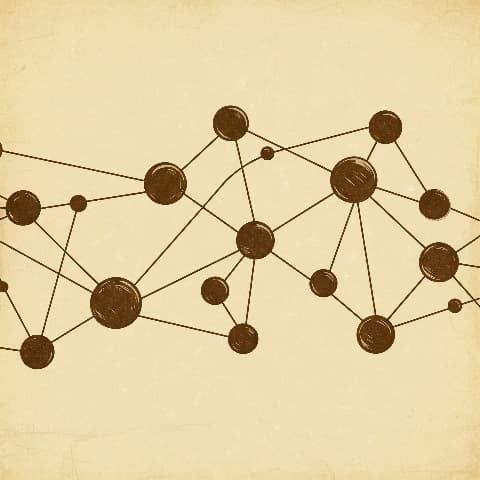
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4741c18f.29752b5e.4741c190.cf23fcaf/?me_id=1398266&item_id=11187682&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fajimura4861%2Fcabinet%2Fa%2F614-1%2F478987978x.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
