なぜ?がスッキリわかる!
スペアナの帯域幅(RBW)を広げるとノイズが強くなる本当の理由
「微弱な信号を探すために、設定を調整していたら…あれ?特に信号を入れていないのに、分解能帯域幅(RBW)を広げただけで、画面全体のノイズレベル(ノイズフロア)がぐわっと上がってきた! なんで?」
これは、RF測定に携わる多くの人が通る、不思議で直感に反する現象です。この記事を最後まで読めば、あなたはこの謎の現象を物理法則のレベルから完全に理解し説明できるようになります。
- 現象の正体: なぜRBWを広げるとノイズだけが大きくなるのか、その決定的な違いを「バケツと水道水」の例えで直感的に理解します。
- 犯人探し: スペアナ内部の「IFフィルタ」の役割を解き明かします。
- 物理の根源: 全ての元凶である「熱雑音」と、それを支配する宇宙の基本法則に迫ります。
- 数学で証明: 「RBWを10倍にするとノイズは10dB上がる」という経験則を、数式を使ってスッキリ証明します。
- 実践知識: この原理が高感度受信機の設計や国際規格(EMC)にどう活かされているかを学びます。
第1部:現象の正体 – 上がっているのは「信号」ではなく「ノイズの総量」
まず結論から言いましょう。RBWを広げたときに増加しているのは、あなたが見たい特定の「信号」の強度ではありません。増加しているのは、空間と測定器自身が常に発している「広帯域ノイズ」のエネルギーの総量なのです。
広帯域ノイズ vs CW信号:振る舞いが全く違う二つの世界
この謎を解く鍵は、「信号」という言葉を二種類に分けて考えることです。
広帯域ノイズ (Broadband Noise)
特徴: エネルギーが特定の周波数に集中せず、まるでバターを薄く塗り広げたように、周波数スペクトル全体に広く分布しています。その代表格が、後で詳しく解説する熱雑音です。
RBWへの反応: RBWを広げると、表示レベルが上昇します。逆に狭めると低下します。
CW(連続波)信号 (Continuous Wave Signal)
特徴: 無変調の信号など、エネルギーがまるで鋭い針のように、たった一つの周波数にぎゅっと集中しています。
RBWへの反応: RBWを(ある程度)広げたり狭めたりしても、そのピークレベルは変化しません。
つまり、スペアナの画面でRBWを操作したときにレベルが変動するものは、ほぼ「ノイズ」や「ノイズに似た性質を持つ信号」だと考えて間違いありません。
アナロジーで直感理解!「バケツで集める雨水」と「蛇口から汲む水」
この違いを、身近な例でイメージしてみましょう。ノイズは地面全体に降り注ぐ「雨水」、RBWは雨水を集める「バケツの口の広さ」に相当します。
たくさんのノイズエネルギーが集まり、表示レベルが高くなる。
集まるノイズエネルギーは少なく、表示レベルは低くなる。
第2部:スペアナの内部を探る – 現象の実行犯は「IFフィルタ」だった
さて、なぜスペアナが「バケツ」のような振る舞いをするのか、その内部構造に迫ってみましょう。多くのスペアナはスーパーヘテロダイン方式という技術で作られています。
ユーザーが設定するRBW(分解能帯域幅)の正体とは、まさにこの「IFフィルタの通過帯域幅」そのものなのです。
(ノイズ + CW)
(ノイズ + CW)
IFフィルタは、その帯域幅内に入ってきた全てのエネルギーを区別なく合計します。だからこそ、フィルタ幅(RBW)が広いほどたくさんのノイズを「合計」し、表示レベルが上がるのです。
第3部:ミクロの世界へ – 全ての元凶「熱雑音」の物理学
では、そもそもその「ノイズ」は一体どこからやってくるのでしょうか?その最も根源的で、決して避けることのできないノイズが熱雑音(ジョンソン・ナイキスト雑音)です。
電子の震えがノイズを生む
絶対零度(-273.15℃)より高い温度を持つ全ての物質では、内部の自由電子が熱エネルギーによってブルブルとランダムに震え(熱擾乱)、動き回っています。この無数の電子たちのランダムな動きが、抵抗の両端に微小な電圧の揺らぎとして現れます。これが熱雑音の正体です。
物理法則が支配するノイズの量:Pₙ = k₈TB
この一見カオスな電子の震えがもたらす雑音の総量は、驚くほどシンプルな物理法則によって支配されています。
k₈: ボルツマン定数 (約 1.38 × 10⁻²³ J/K)
T: 絶対温度 (K)
B: 帯域幅 (Hz) ← これがRBWに相当
この式が示している、最も、最も重要な結論は、「熱雑音の総電力(Pₙ)は、それを観測する帯域幅(B)に完全に正比例する」という事実です。
RFエンジニアの魔法の数字「-174 dBm/Hz」
この物理法則から、全てのRFエンジニアが暗記している「魔法の数字」が生まれます。室温 (T=290 K) で、帯域幅を1Hzに限定した場合のノイズ電力を計算すると、-174 dBm/Hz という値が得られます。
これは、「室温において、1Hzという非常に狭い幅でノイズを測定したときの理論的な最小電力」を示し、あらゆる受信システムが超えることのできない、物理的な感度の限界です。
第4部:数学でスッキリ!「RBWが10倍でノイズフロアが10dB上昇」の法則
パワー・スペクトル密度(PSD)という考え方
これは、「-174 dBm/Hz」のように、「単位周波数(1Hz)あたりの電力」を表す「密度」の考え方です。
(バケツに溜まった水の総量)
(地面に降る雨の激しさ)
このPSDを使うと、スペアナが表示するノイズ電力は、測定ノイズ電力 ≈ PSD × RBW という非常にシンプルな関係で表現できます。
デシベルの世界で法則を証明しよう
この関係式をデシベルに変換すると、掛け算は足し算になります。
この式を使って、RBWを10倍にしたときに何が起こるか見てみましょう。
// 元のRBWと測定電力 P₁ = PSD + 10log₁₀(RBW₁) // RBWを10倍にする RBW₂ = 10 × RBW₁ // 新しい測定電力 P₂ = PSD + 10log₁₀(RBW₂) = PSD + 10log₁₀(10 × RBW₁) // 対数の法則 log(a×b) = log(a) + log(b) を使う P₂ = PSD + 10log₁₀(10) + 10log₁₀(RBW₁) // 10log₁₀(10) = 10 dB なので P₂ = (PSD + 10log₁₀(RBW₁)) + 10 dB = P₁ + 10 dB
証明完了です! これにより、RBWを10倍にすると、測定されるノイズフロアが正確に10dB上昇することが数学的に示されました。
第5部:この原理をどう活かすか?
ケースA:雑音の中から「微弱な信号」を探し出す場合
目的: ノイズの海の中から、特定の周波数に存在する「微弱な信号」を見つけ出すこと。
対策: スペクトラムアナライザの帯域幅(RBW)を狭くします。
理由: RBWを狭くすると、集めるノイズの総量が減るためノイズフロアだけが下がります。一方、CW信号のピークレベルは変わらないため、信号がノイズから浮かび上がって見えるようになります。これが「感度(S/N比)が向上した」状態です。
ケースB:「広帯域ノイズそのもの」の電力を測定する場合
目的: ある広い周波数範囲にわたって存在する「ノイズそのもの」の総電力を正確に測定すること。
対策: 前置増幅器の帯域幅を広くします。
理由: 広帯域ノイズの総電力を正確に測るには、測定したい周波数範囲のノイズをすべて取りこぼさずに集めてくる必要があります。もし前置増幅器の帯域幅が狭いと、その増幅器がフィルタとして働き、測定したいノイズの一部をカットしてしまいます。
アンプなどの電子部品は、信号を増幅するだけでなく、自分自身でも熱雑音などを発生させ、信号に余分なノイズを加えてしまいます。この「デバイスがどれだけノイズを加えるか」を示す性能指数がノイズフィギュア(Noise Figure, NF)です。NFは小さいほど優秀です。
複数の部品(プリアンプ、ミキサーなど)を繋いで受信機を設計するとき、システム全体のNFはどうなるのでしょうか?ここで登場するのがフリースの伝達公式です。
(FはNFを、Gはゲインをリニア値に変換したものです)
この式が示す、設計における極めて重要な教訓は、「総合的なノイズ性能は、圧倒的に初段(一番最初の部品)の性能で決まる」ということです。
2段目以降の部品が加えるノイズ(F2, F3…)は、初段のゲイン(G1)で割り算されるため、影響が非常に小さくなります。
このため、高感度な受信機を設計する際には、必ずシステムの入り口に「低ノイズ(低NF)」で「高ゲイン」なプリアンプ(LNA)を置くのが絶対的なセオリーなのです。これもまた、雑音電力が帯域幅に依存するという基本原理の上に成り立つ、システム設計の根幹です。
測定の公平性と再現性を確保するため、国際規格(CISPRなど)によって測定する周波数帯ごとに使用するRBWが厳密に定められています。以下は一例です。
| 周波数帯 | 規定RBW (-6dB) |
|---|---|
| 9 kHz – 150 kHz | 200 Hz |
| 150 kHz – 30 MHz | 9 kHz |
| 30 MHz – 1 GHz | 120 kHz |
| 1 GHz – 18 GHz | 1 MHz |
(出典: CISPR ✖️✖️-✖️-✖️に基づく(一例))
さあ、これまでに学んだ知識を使って、具体的な問題を解いてみましょう!
例題1:基本のRBWとノイズフロア計算
問題: あるスペアナのノイズフロアが、RBW = 100 kHz の設定で -100 dBm と表示されています。RBWを 10 kHz に変更した場合、ノイズフロアは何dBmになりますか?
解法:
RBWを 100 kHz から 10 kHz へ、1/10 に変更しました。ノイズフロアの変化量は、以下の式で計算できます。
したがって、新しいノイズフロアは、元の値から10dB低下します。
例題2:微弱信号の検出に必要なRBWを求める
問題: ノイズのPSDが -165 dBm/Hz の環境で、-130 dBm の微弱なCW信号を、ノイズフロアより 15 dB 以上高く表示させたいです。RBWを最大で何Hzに設定する必要がありますか?
解法:
1. 目標とするノイズフロアを決定します。 信号(-130 dBm)より15 dB低くしたいので、目標ノイズフロアは、
2. 関係式を使ってRBWを計算します。Noise Floor (dBm) = PSD (dBm/Hz) + 10log10(RBW)
答え: RBWを 100 Hz 以下に設定する必要があります。
例題3:【チャレンジ】受信システムのS/N比を改善する
問題: 帯域幅 10 MHz の通信システムで、-85 dBm の信号を受信しています。このシステムのNFは 6 dB です。
1. 現在の信号対雑音比(SNR)は何dBですか?
2. もし、信号処理技術で実効的な帯域幅を 50 kHz まで狭めることができたら、SNRは何dB改善されますか?
解法:
1. 現在のノイズ電力とSNRを計算します。 基準熱雑音密度は -174 dBm/Hz です。Pnoise = (熱雑音密度) + 10log10(帯域幅) + NF
SNRは信号電力とノイズ電力の差なので、
2. 帯域幅を狭めた場合のSNRと改善量を計算します。 帯域幅を 50 kHz にした場合のノイズ電力を再計算します。
新しいSNRは、
SNRの改善量は、
答え: SNRは 23 dB 改善されます。帯域幅を狭めることが、いかに強力なノイズ対策であるかが分かりますね。
結論:物理原理の理解が、あなたの測定を革新する
スペアナのRBWを広げると表示強度が上がる現象は、単なる測定器の特性ではなく、ミクロな電子の振る舞いを支配する、普遍的な物理法則の直接的な現れだったのです。
- 主因は熱雑音: 表示レベルが上がるのは、広く分布する「熱雑音」を、より広い「窓(RBW)」で集めているからです。
- 物理法則が支配: この現象は、Pₙ = k₈TB という普遍的な物理法則の現れです。
- CW信号との対比が鍵: エネルギーが集中したCW信号のレベルはRBWに依存しない、この違いの理解が不可欠です。
真に優れたエンジニアリングは、表面的な操作の習熟ではなく、その背後にある物理原理への深い洞察から生まれるのです。
たび友|サイトマップ
関連webアプリ
たび友|サイトマップ:https://tabui-tomo.com/sitemap
索友:https://kentomo.tabui-tomo.com
ピー友:https://pdftomo.tabui-tomo.com
パス友:https://passtomo.tabui-tomo.com
クリプ友:https://cryptomo.tabui-tomo.com
進数友:https://shinsutomo.tabui-tomo.com

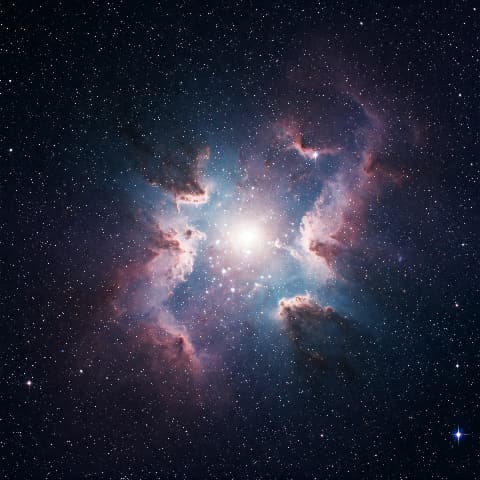
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=11895460&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7898%2F78983722.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=13693096&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0972%2F9784789840972.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

