【完全版】電子機器ノイズの9割を占める犯人の正体!
「コモンモード」を世界一わかりやすく解説
「苦労して設計した回路が、最後のノイズ試験でまさかの不合格…」
「原因不明の誤動作に頭を悩ませている…」
この記事では、そんな電子機器設計における最大の敵、電磁波ノイズの根本原因である「コモンモード電流」と、本来の信号である「ディファレンシャルモード電流」の違いについて、そしてわかりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には…
- なぜノイズが発生するのか、そのメカニズムが理解できる。
- ノイズ問題の「コモンモード」の正体を突き止められる。
- 難解な数式が示す物理的な意味を直感的に把握できる。
すべての基本!ディファレンシャルモードとコモンモード
電子回路で発生するノイズを理解するための最初の、そして最も重要なステップは、電流の振る舞いを2つの「モード」に分けて考えることです。それがディファレンシャルモードとコモンモードです。
そもそも、なぜ2つのモードを考える必要があるの?
私たちの目的は、意図した信号(例えば、音楽データやセンサーの値)を正しく伝えることです。しかし、現実の回路では、この意図した信号に加えて、意図しない様々なノイズが乗り込んできます。
この複雑な現象を整理し、対策を立てるために、ノイズの伝わり方をモデル化する必要があるのです。
ディファレンシャルモード: 2人の間で交わされる「会話」の流れ。これには、伝えたい「声(信号)」と、「咳払いや言い間違いなど(ノイズ)」の両方が含まれます。
コモンモード: 周囲の「ざわめき」や「雑音」。糸電話の糸全体が揺れて、会話そのものを邪魔します。
このように、ディファレンシャルモードにもノイズは存在しますが、コモンモードノイズとはその性質と影響の大きさが全く異なります。それぞれの正体を見ていきましょう。
ディファレンシャルモード:回路の主役と、その経路に乗るノイズ
ディファレンシャルモード(別名:ノーマルモード)は、電子回路が機能するために設計された、本来あるべき電流の姿です。
その最大の特徴は、電流の「行き」と「帰り」の道が明確に決まっていることです。
- 電流の方向: 「行き」の導体と「帰り」の導体を流れる電流の向きが正反対です。
- 電流の大きさ: 「行き」と「帰り」の電流の大きさが等しいです。
この対向性により、それぞれが発生させる磁界が遠くの地点で互いに打ち消し合うため、外部への電磁波放射が非常に少なくなるのです。
この経路には、私たちが伝えたい「意図した信号」が流れます。しかし、同時にこの経路には「ディファレンシャルモードノイズ」も乗ってきます。例えば、電源回路におけるスイッチングによって発生するリップルノイズなどがその代表例です。これらは信号線とリターン線の間を信号と同じように伝わるため、回路の誤動作の原因となることがあります。
しかし、放射EMIという観点で見ると、ディファレンシャルモードノイズは、その放射効率の低さから、次に説明するコモンモードノイズほど深刻な問題になるケースは少ないのが実情です。
コモンモード:ノイズ界の真犯人(意図しないノイズ)
一方、コモンモードは回路の機能には全く貢献しない、百害あって一利なしの存在です。これがEMI(電磁干渉)問題の主犯格とされています。
その特徴は、ディファレンシャルモードとは真逆です。
- 電流の方向: 2本以上の導体(例えば信号線とGND線)を、同じ向きの電流が流れます。
- 帰り道が不明: 本来の帰り道を使わず、グラウンドプレーンや機器の金属ケース、接続されたケーブルなど、予期せぬ広大なルートを通って戻ろうとします。
同じ向きの電流が流れるため、それぞれの導体から発生する磁界は同じ方向を向き、互いに強め合います。さらに、帰り道が遠く広大なため、電流のループ全体が巨大なアンテナのように振る舞ってしまいます。
※ここでのループアンテナは波長に対して小さなループアンテナを想定しています。実際は、ループ面積が大きくなるとダイポールアンテナとしての振る舞いも大きくなるため、面積が大きくなるほど放射ノイズが大きくなるとは限りませんのでご注意ください。
その結果、コモンモード電流は、たとえその量が信号電流のごく微量であっても、非常に強力な電磁波を放射してしまうのです。
| 特性 | ディファレンシャル(ノーマル)モード | コモンモード |
|---|---|---|
| 電流方向 | 逆方向 | 同一方向 |
| 性質 | 意図された信号と、その経路上のノイズ | 意図しない寄生的なノイズ |
| リターンパス | 専用の隣接導体 | 意図しない経路(GND、筐体など) |
| 磁界の振る舞い | 打ち消し合う | 強め合う |
| 放射効率 | 低い | 非常に高い |
キーポイント: ノイズ対策で本当に重要なのは、いかにして「コモンモード」という真犯人を発生させないか、という点に尽きます。
なぜ真犯人は生まれるのか?コモンモード発生のメカニズム
コモンモード電流は自然に発生するわけではありません。本来、完璧にバランスが取れているはずの回路に、何らかの「不平衡」や「非対称性」が生じたときに、ディファレンシャルモードのエネルギーの一部が悪役のコモンモードへと姿を変えてしまうのです。この現象を「モード変換」と呼びます。
非対称性
では、その「不平衡」はどこからやってくるのでしょうか?
原因1:幾何学的な非対称性(見た目のズレ)
設計図の上では完璧に見えても、物理的なレイアウトには必ず微細なズレが生じます。
- 配線長の不整合(スキュー): 差動信号(例: USB、HDMI)のペア線を構成する2本の配線の長さがわずかでも異なると、信号が受信端に到着するタイミングがズレます。このほんのわずかなタイミングのズレ(数ピコ秒レベル!)が、信号の立ち上がり・立ち下がりの瞬間に不平衡を生み、コモンモードノイズを発生させるのです。
- 非対称な配線経路: 配線の曲がり方、ビア(基板の層を繋ぐ穴)の数や配置がペアで異なると、局所的にインピーダンスが乱れ、バランスが崩れます。
原因2:部品やドライバの不整合(性能のバラつき)
電子部品は工業製品であるため、必ず性能に個体差(公差)があります。
- ドライバの不整合: 差動信号を送り出すICのプラス側とマイナス側の出力特性(電圧の高さ、立ち上がり時間など)が完全に一致していないと、信号の発生源の時点ですでに不平衡が生じています。
- 部品の公差: 終端抵抗などの値がペア間で異なると、インピーダンスの不整合から信号の反射が起こり、電流のバランスが崩れます。
原因3:高周波のイタズラ(見えない寄生素子)
回路図には描かれない、しかし高周波領域では無視できない「寄生」的な部品が存在します。これが最も厄介な不平衡の原因です。
- 浮遊容量の非対称性: 配線とグラウンドや金属ケースとの距離がペア間で異なると、そこに「意図しないコンデンサ(浮遊容量)」が形成されます。周波数が高くなるほど、信号電流はこのコンデンサを通してグラウンドへ漏れ出しやすくなります。この漏れ出す量が左右で異なれば、その差がそのままコモンモード電流となってしまうのです。
最も重要な原因:「完璧なグラウンド」は存在しない
私たちはつい「グラウンド(GND)は電位0Vの理想的な基準面」と考えてしまいがちですが、これは低周波での近似に過ぎません。
現実のグラウンドプレーンは有限のインピーダンス(電気抵抗のようなもの)を持っています。そのため、大きな電流が流れると電圧降下が生じ、場所によって電位が異なる「ノイジーな」状態になります(グラウンドバウンス)。
信号線がこのノイジーなグラウンドを基準にしていると、グラウンドのノイズが直接信号線に乗り移り、強力なコモンモード電流を発生させる原因となるのです。
キーポイント: コモンモードの発生は単一の要因ではなく、設計に内在する多くの微小な非対称性が積み重なった結果です。EMC設計とは、この「対称性」をいかに維持するかという戦いなのです。
なぜコモンモードは凶悪なのか?放射の物理学
「コモンモード電流はごく僅かでも強力なノイズを出す」と述べましたが、それは一体なぜなのでしょうか?その答えは、電流が流れる構造がどのような「アンテナ」として振る舞うかに隠されています。
(非効率なループアンテナ)
ループ面積が小さく、放射効率は低い。
(超効率的なダイポールアンテナ)
アンテナ長が長く、放射効率は極めて高い。
ディファレンシャルモード放射:非効率な「ループアンテナ」
ディファレンシャルモードでは、電流は「行き」の信号線とそのすぐ近くにある「帰り」の線で、小さな閉じたループを形成します。この構造は、電気的に「微小ループアンテナ」と等価です。
微小ループアンテナからの放射電力は、ループの面積と周波数の4乗に比例します。EMCの基本設計では、リターンパスを信号線の直下に配置してこのループ面積を意図的に最小化します。そのため、ディファレンシャルモードは本質的に非常に放射効率の低いアンテナとなるのです。
コモンモード放射:超効率的な「ダイポールアンテナ」
一方、コモンモードでは、電流はケーブルや基板パターンを一方向に流れ、遠く離れたグラウンドや筐体を経由して戻ります。この構造は、もはや小さなループではなく、むしろ「ダイポールアンテナ」や「モノポールアンテナ」として機能します。
例えば、機器に接続されたケーブルにコモンモード電流が流れると、そのケーブル全体がアンテナとなり、機器の筐体が大地(グラウンドプレーン)の役割を果たします。
これらのアンテナは、その物理的な長さが信号の波長に対して無視できない割合(例えば1/4波長など)になると、ループアンテナとは比較にならないほど効率的に電磁エネルギーを放射します。
ディファレンシャルモードとコモンモードの放射効率には、どれほどの差があるのでしょうか?その答えは、放射電界強度を計算する数式を比較すると一目瞭然です。
【数式】
アンテナから十分に離れた遠方界における最大電界強度 Emax は、それぞれのモードで以下のように近似できます。
ディファレンシャルモード(ループ)放射:
ED,max ∝ ID ⋅ S ⋅ f2
(電流 ID、ループ面積 S、周波数 f の2乗に比例)
コモンモード(ダイポール)放射:
EC,max ∝ IC ⋅ L ⋅ f
(電流 IC、アンテナ長 L、周波数 f の1乗に比例)
これらの式を実用的なある定数で比較すると、コモンモード放射の係数はディファレンシャルモードの係数より実に1000万倍以上も大きいことがわかります。
結論だけ知りたい方へ:
ある計算例では、ディファレンシャルモード電流のわずか1/2500(-68dB)の大きさのコモンモード電流が、同レベルの放射ノイズを発生させることが示されています。
問題は電流の大きさではなく、電流がどちらの「モード」で流れているかなのです。これが、EMI対策でコモンモード電流の抑制に全力を注がなければならない絶対的な理由です。
ノイズを制圧せよ!明日から使える実践的対策
コモンモードという悪役の正体とその恐ろしさがわかったところで、いよいよ具体的な対策を見ていきましょう。対策は大きく分けて「伝搬経路(ケーブル)」「発生源(基板)」「部品によるフィルタリング」の3つの階層で考えます。
対策1:ケーブル&コネクタ(最大のアンテナを無力化する)
機器から伸びるケーブルは、最も効率的な放射アンテナになりがちです。ここを制圧することが第一の防衛線となります。
ツイストペアケーブル(撚り対線)
LANケーブルなどでお馴染みの、2本の導体を撚り合わせたケーブルです。この単純な構造が、非常に強力なディファレンシャルモードなどのノイズ対策になります。
- ノイズを拾いにくい: 外部からのノイズ磁界によって各ツイストで発生する誘導電圧が、次のツイストで逆向きに発生する電圧と相殺されます。
- ノイズを出しにくい: 内部のディファレンシャル電流が作る磁界も、同様に各ツイストで打ち消し合い、外部への放射を抑制します。
ツイストペアは、ペアの平衡(対称性)を維持するための、最もシンプルで効果的な手法です。
シールドケーブル
ケーブルを金属の編組や箔で覆うシールドは、外部からのノイズを遮断し、内部からのノイズ漏洩を防ぐのに有効です。しかし、その効果は接地(グラウンディング)の方法や整合性に依存するという、非常に重要な注意点があります。
- 片端接地: シールドを片側だけで接地する方法。グラウンドループを防げますが、高周波では接地していない側がアンテナになり、ノイズを拾ったり放射したりする弱点があります。
- 両端接地: シールドを両端で接地する方法。高周波ノイズには効果的ですが、接続機器間に電位差があると、シールド自体に大きなグラウンドループ電流(コモンモード電流)が流れる危険性があります。
警告: ノイズを防ぐためのシールドが、不適切な接地によって、それ自体が最悪のコモンモードアンテナとなり、かえって問題を悪化させることが頻繁にあります。
対策2:プリント基板(PCB)レイアウト(発生源を叩く)
「回路図は嘘をつく」。高周波の世界では、部品の物理的な配置(レイアウト)こそが回路の真の性能を決定します。
最重要原則:グラウンドプレーンを分断するな!
低ノイズ設計における最も重要なルールは、「信号線の直下に、分断のないベタのグラウンドプレーンを基準として用意すること」です。これにより、電流の帰り道(リターンパス)は、ループ面積が最小となるように自然と信号線の真下を流れ、ディファレンシャルモードが綺麗に保たれます。
絶対にやってはいけないこと: 高速信号の配線を、グラウンドプレーンのスリットやギャップをまたいで配線することです。これは、リターン電流に広大な迂回を強いることになり、意図せずして巨大なループアンテナを形成します。これはモード変換と強力なEMI放射の典型的な原因であり、EMI試験で不合格となる設計の代表例です。
高速配線の鉄則
- インピーダンス制御: 配線幅と基準プレーンからの距離を一定に保ち、特性インピーダンスを維持します。
- 差動ペアの配線: ペアは常に等長かつ平行に、できるだけ近く配線し、対称性を徹底的に維持します。
- 基板の端を避ける: 基板の端付近はリターン電流の経路が乱れやすいため、高速信号の配線は避けるべきです。
対策3:ノイズ対策部品
設計を工夫しても取り切れないノイズは、専用の部品を使って抑制します。
コモンモードチョークコイル(CMCC)
コモンモードノイズ対策の切り札とも言える、非常に効果的な部品です。
ディファレンシャルモードに対して: 逆向きの電流が流れるため、磁束が打ち消し合い、ただの電線のように振る舞います(低インピーダンス)。信号には影響を与えません。
コモンモードに対して: 同じ向きの電流が流れるため、磁束が強め合い、大きなインダクタンス(コイル)として機能します(高インピーダンス)。これにより、コモンモード電流の流れを強力に阻止します。
ケーブルからの放射を防ぐため、I/Oコネクタのできるだけ近くに配置するのが最も効果的です。
Xコンデンサ、Yコンデンサ
主に電源ラインのフィルタに使用されるコンデンサです。
- Xコンデンサ: 電源ライン間(L-N間)に接続し、ディファレンシャルモードノイズをバイパスさせます。
- Yコンデンサ: 各電源ラインと筐体グラウンド間に接続し、コモンモードノイズをグラウンドへ逃がします。
知識を力に!実践問題とまとめ
理論を学んだところで、具体的なシナリオに基づいた問題を通じて理解を深めてみましょう。
実践問題1:どっちがうるさい?電界強度を計算してみよう
シナリオ: 長さ1mのケーブルで機器が接続されており、30MHzの信号が流れています。測定の結果、ディファレンシャルモード電流(iD)は20mA、しかし何らかの不平衡により、そのわずか1/2000である10µAのコモンモード電流(iC)も流れていました。距離3m地点での放射ノイズはどちらが支配的でしょうか?
導体間隔(h)を0.5mとし、ループ面積(A)を 0.5×10-6 m2 とする。)
計算:
資料に記載されている実用計算式を用いると…
コモンモード放射:
[V/m の計算過程]
式: E = (2π×10-7 ⋅ iC ⋅ L ⋅ f) / r
代入: (6.28×10-7 ⋅ 1×10-5 ⋅ 1 ⋅ 3×107) / 3
分子: 18.84×10-5
結果: 18.84×10-5 / 3 ≈ 6.28×10-5 V/m
EC,max ≈ 6.28×10-5 V/m
→ 20 × log10(6.28×10-5 / 10-6)
→ 20 × log10(62.8)
→ 36 dBµV/m
ディファレンシャルモード放射:
[V/m の計算過程]
式: E = (2.63×10-14 ⋅ iD ⋅ A ⋅ f2) / r
代入: (2.63×10-14 ⋅ 0.02 ⋅ 0.5×10-6 ⋅ (3×107)2) / 3
分子: 0.2367×10-6
結果: 0.2367×10-6 / 3 ≈ 7.9×10-8 V/m
ED,max ≈ 7.9×10-8 V/m
→ 20 × log10(7.9×10-8 / 10-6)
→ 20 × log10(0.079)
→ -22 dBµV/m
結論:
驚くべきことに、電流の大きさでは2000倍も小さいコモンモードの方が、放射ノイズのレベルでは約58dBも大きい(電圧で約800倍!)という結果になりました。これは、一般的な放射エミッション規制値を超える可能性が高いレベルです。この計算結果は、EMI問題の支配的要因は、ほぼ常にコモンモード放射であるという事実を定量的に裏付けています。
実践問題2:致命的な基板レイアウトミスを探せ!
シナリオ: ある設計者が、高速なUSB信号の差動ペア線を、デジタルグラウンドとアナロググラウンドを分離する3mm幅のスリットをまたいで配線してしまいました。このシステムは、高周波の放射エミッション試験で不合格となりました。何が問題で、どうすればよかったのでしょうか?
分析:
- 問題点: グラウンドプレーンのスリットは、信号の直下を流れるべきリターン電流の経路を物理的に遮断してしまいます。
- 何が起こるか: 行き場を失ったリターン電流は、スリットを迂回して最も近い接続点まで、非常に大きなループを描いて戻らざるを得なくなります。この巨大なループがインピーダンスの不平衡を生み、ディファレンシャルモードのエネルギーを効率的にコモンモード電流へと変換します。発生したコモンモード電流は、接続されたUSBケーブルをアンテナとして機能させ、強力な電磁波を放射します。
修正案:
- 最善策: 配線経路を変更し、差動ペアがスリットをまたがないようにするのが鉄則です。
- 次善策: どうしても配線変更が不可能な場合、スリットを橋渡しするように「スティッチング・キャパシタ」を配置し、高周波のリターン電流に近道を提供する方法もありますが、これはあくまで妥協策です。
実践問題3:最適なノイズ対策部品を選定しよう
シナリオ: 長さ2mの電源ケーブルを持つ装置が、150MHzの放射エミッションで規格値(30 dBµV/m @ 10m)を大幅に超過してしまいました。診断の結果、原因は電源ケーブル上の50µAのコモンモード電流だと判明しました。このノイズを抑えるには、どれくらいの性能を持つコモンモードチョーク(CMCC)が必要でしょうか?システムのインピーダンスは約100Ωとします。
計算プロセス:
-
現状の放射レベルを計算:
[V/m の計算] ※iC=50µA, L=2m, f=150MHz, r=10m の場合 式: E = (2π×10-7 ⋅ iC ⋅ L ⋅ f) / r 代入: (6.28×10-7 ⋅ 5×10-5 ⋅ 2 ⋅ 1.5×108) / 10 分子: 94.2×10-4 結果: 94.2×10-4 / 10 = 9.42×10-4 V/mEC,max ≈ 9.42×10-4 V/m → 約 59.5 dBµV/m
[V/mからdBµV/mへの変換] 式: レベル[dBµV/m] = 20 × log10( 電界強度[V/m] / 10-6 ) 代入: 20 × log10( 9.42×10-4 / 10-6 ) → 20 × log10(942) → 20 × 2.974 → 59.48 -
必要な減衰量を計算:
[目標値との差分を計算] 現状レベル: 59.5 dBµV/m 規制値 (目標): 30 dBµV/m 計算: 59.5 – 30 = 29.5 dB59.5 dBµV/m – 30 dBµV/m = 29.5 dB→ 安全マージンを見て、30dBの減衰を目指します。
-
必要なチョークのインピーダンスを計算:
[減衰量からインピーダンスを逆算] 式: Zchoke = Zsys (10(Attenuation/20) – 1) ※コモンモード系のインピーダンス(Zsys)を100Ωと仮定 代入: 100 × (10(30/20) – 1) → 100 × (101.5 – 1) → 100 × (31.62 – 1) → 100 × 30.62 → 3062ΩZchoke = 100(10(30/20) – 1) ≈ 3060Ω
結論:
この問題を解決するには、150MHzにおいて、少なくとも3060Ω以上のコモンモードインピーダンスを持つCMCCを選定し、電源ケーブルの根元に挿入する必要がある、ということがわかります。
低EMI設計のための黄金律
最後に、効果的なEMI制御のための主要原則をまとめます。
発生源で抑制せよ (Source Control)
- 信号の立ち上がり時間は、必要以上に速くしない。
- リンギングを抑制するため、適切な終端やダンピング抵抗を使用する。
伝搬経路を管理せよ (Path Control)
- 電流のリターンパスを常に意識せよ。分断のない低インピーダンスの基準プレーンを提供する。これが最も重要です。
- 回路の対称性を維持するために、差動ペアは等長・緊密に配線する。
最終防衛ラインを固めよ (Filtering and Shielding)
- ケーブルの出入り口には、コモンモードチョークなどのフィルタを配置し、ノイズの流出を防ぐ。
- シールドの接地は、その性能を決定づけることを理解し、正しく施工する。
たび友|サイトマップ
関連webアプリ
たび友|サイトマップ:https://tabui-tomo.com/sitemap
索友:https://kentomo.tabui-tomo.com
ピー友:https://pdftomo.tabui-tomo.com
パス友:https://passtomo.tabui-tomo.com
クリプ友:https://cryptomo.tabui-tomo.com
進数友:https://shinsutomo.tabui-tomo.com

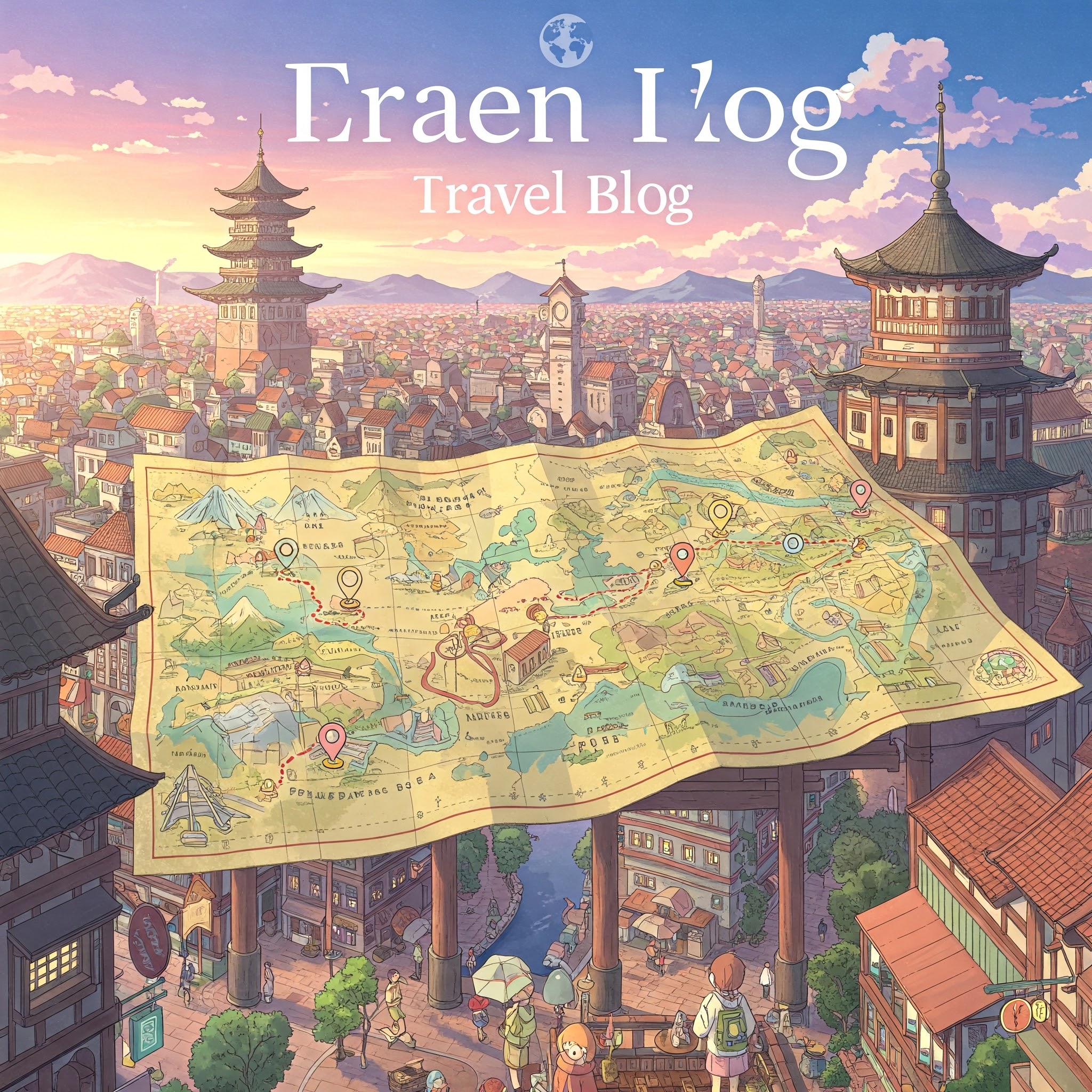
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=21190986&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6291%2F9784320036291_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=20931764&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1513%2F9784627761513.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

