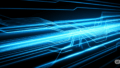【完全版】雑音指数(NF)とフリスの公式を世界一わかりやすく解説|通信品質の謎を解き明かす
「スマホの電波が悪い…」「ラジオに『サー』というノイズが入る…」
私たちの日常にあふれるこんな不満。その原因が、実は宇宙の始まりにまで遡る物理現象と、それを克服するためのエンジニアたちの壮絶な戦いにあるとしたら、少し興味が湧きませんか?
この記事では、通信システムの品質を左右する「見えない敵」である雑音(ノイズ)の正体を暴き、それと戦うための最強の武器であるS/N比、雑音指数(NF)、そして受信機設計の心臓部ともいえるフリスの公式について解説します。
📝 この記事でわかること
- 雑音の正体: なぜノイズは絶対に避けられないのか?
- S/N比: 通信品質を示す最も基本的なモノサシとは?
- 雑音指数 (NF): 機器の「静かさ」をどう測るのか?
- フリスの公式: なぜ受信機の「初段」が命なのか?
- 実践的な計算: 演習問題を通して、理論がどう実務で使われるかがわかる!
通信工学を学ぶ学生、資格試験に挑む方、そして現場で活躍する若手エンジニアまで、すべての人が「わかった!」と膝を打つ内容をお届けします。さあ、ノイズとの静かなる戦いの世界へようこそ。
第1部 すべてはここから始まる:雑音(ノイズ)という避けられない敵
あらゆる通信は、「雑音」との戦いです。特に、衛星通信のように宇宙の彼方から届く微弱な信号を扱うシステムにとって、雑音は情報を奪う最大の脅威となります。
なぜ雑音は発生するのか?熱雑音の正体
通信システムに存在する数ある雑音の中でも、最も普遍的で、決して避けることのできないものが熱雑音(サーマルノイズ)です。
起源: この雑音は、温度を持つすべての導体(ケーブル、抵抗など)の内部で、電子が不規則に振動すること(熱運動)によって自然に発生します。
性質: 温度が高いほど電子の動きは激しくなり、熱雑音も大きくなります。これは物理法則に根ざしているため、部品を絶対零度(-273.15℃)まで冷却する以外に根本的な除去は不可能です。
熱雑音の大きさを測る:ナイキストの定理 Pn = kTB
では、この厄介な熱雑音の大きさはどうやって決まるのでしょうか。それを数式で示したのがナイキストの定理です。
ある帯域幅 B [Hz] で取り出せる最大の熱雑音電力 Pn は、以下の非常にシンプルな式で表されます。
- k: ボルツマン定数 (約 1.38 × 10-23 J/K)
- T: 絶対温度 [K]
- B: 帯域幅 [Hz]
ここで驚くべきは、この式に抵抗値 R が含まれていないことです。つまり、インピーダンスが同じであれば、どんな材質の抵抗であろうと、同じ温度・同じ帯域幅なら全く同じ雑音電力を発生させるのです。これにより、雑音を標準化して扱うことが可能になります。
魔法の数字
通信業界では、慣例として基準温度を T0 = 290 K (約17℃) と定めており、この時の1Hzあたりの雑音電力密度 (kT0) は -174 dBm/Hz となります。これは、RFエンジニアが常に頭に入れておくべき魔法の数字です。
第2部 通信品質のモノサシ:S/N比とその仲間たち
雑音の正体がわかったところで、次はその影響を評価するための指標を見ていきましょう。その最も基本的で直感的な指標が信号対雑音比(S/N比、SNR)です。
S/N比 (信号対雑音比) とは?
S/N比とは、その名の通り「受信したい信号 (Signal) の電力」と「邪魔な雑音 (Noise) の電力」の比率です。
真数表現: SNR = Ps⁄Pn
デシベル(dB)表現: SNRdB = 10 log10 (Ps⁄Pn)
例えば、信号電力が雑音電力の100倍なら、S/N比は 10 log10(100) = 20 dB となります。S/N比が高いほど、通信品質が良いことを意味します。アナログ通信ならクリアな音声に、デジタル通信ならエラーの少ないデータ伝送に繋がります。
【デジタル通信編】知っておくべきS/N比の親戚たち
デジタル通信の世界では、システムの性能をより精密に評価するため、S/N比から派生したいくつかの専門指標が使われます。特に資格試験ではこれらの違いが頻繁に問われるため、しっかり理解しましょう。
| 指標 (Metric) | 定義 (Definition) | 式 (Formula) | 主な用途 (Primary Use Case) |
|---|---|---|---|
| S/N, C/N | 信号(搬送波)電力と帯域内総雑音電力の比 | Ps / (N0B) | システム最終段での総合的な信号品質評価 |
| C/N₀ | 搬送波電力と雑音電力密度(1Hzあたり)の比 | C / N0 | 帯域幅に依存しないリンク品質の評価 |
| Eb/N₀ | 1ビットあたりのエネルギーと雑音電力密度の比 | (C/N0) / R | デジタル変調・符号化方式のBER性能の正規化比較 |
- C/N₀ (搬送波対雑音電力密度比): 受信機の帯域幅に依存しないため、通信経路そのものの品質(リンク品質)を公平に比較するのに役立ちます。
- Eb/N₀ (1ビットあたりのエネルギー対雑音電力密度比): デジタル通信において最も本質的な指標です。この値さえ分かれば、どんな変調方式(QPSK, 16QAMなど)を使った時に、どれくらいのビット誤り率(BER)になるかを理論的に予測できるのです。まさに、物理層(電力)と情報層(ビット)を繋ぐ架け橋となる指標です。
第3部 性能劣化の犯人:雑音指数 (NF) と雑音温度 (Te)
理想的な機器は信号を増幅するだけですが、現実の増幅器(アンプ)などは、信号を処理する過程で自らも雑音を発生させてしまいます。その結果、入力された信号は、出力される際には必ずS/N比が劣化します。
この「S/N比がどれだけ劣化したか」を示す指標が、雑音指数(Noise Figure, NF)です。
【図解】機器によるS/N比の劣化イメージ
増幅器など
(Gain, NF)
雑音指数 (NF) の定義
雑音指数は、入力S/N比と出力S/N比の比で定義されます。
雑音係数 (F): F = SNRin⁄SNRout (真数値)
雑音指数 (NF): NFdB = 10 log10(F) (デシベル値)
雑音を全く発生しない理想的な機器では、 F=1、NF=0 dB となります。NFの値が小さいほど、その機器は「低雑音で高性能」だと言えます。
物理的に見ると、NFの本質は機器が内部で生み出す付加雑音 (Nadded) です。雑音係数Fのうち、「1」を超える部分 (F−1) こそが、この付加雑音の大きさを表しています。
もう一つの指標:雑音温度 (Te)
NFは非常に便利な指標ですが、基準温度 T0=290 K に依存するという弱点があります。衛星通信のアンテナが極低温の宇宙空間を向いている場合など、実際の環境が290Kと大きく異なるとき、NFは劣化度を正確に表せなくなります。
そこで登場するのが、より物理的で普遍的な雑音温度 (Noise Temperature, Te) です。
定義: その機器が発生する付加雑音と、同じだけの熱雑音を発生する仮想的な抵抗の温度。
NFとの関係: 以下の式で相互に変換可能です。
雑音温度は、信号源の温度に依存しないため、どんな環境でも機器の「静かさ」を絶対的に評価できます。特に、極低雑音が求められる電波天文学や深宇宙通信では、NFよりも雑音温度が重要な指標として使われます。
第4部 受信機設計の最重要法則:フリスの公式
実際の受信機は、アンテナ、増幅器、ミキサなど、多数の機器がリレーの走者のように縦続(カスケード)接続されています。この「チーム全体」の雑音性能はどう決まるのでしょうか?その答えを教えてくれるのが、フリスの雑音公式です。
フリスの公式とは?
n個の機器が接続されたシステム全体の総合雑音係数 Ftotal は、以下の式で与えられます。
- Fi: i番目の機器の雑音係数(真数)
- Gi: i番目の機器の電力利得(真数)
🚨最重要注意点🚨
この計算を行う際は、NF(dB)や利得(dB)を必ず真数値の F と G に変換しなければなりません。これは初学者が最も陥りやすい間違いです。
公式が教える残酷な真実:「初段がすべて」
この式をよく見てください。何か気づくことはありませんか?
【図解】フリスの公式が示す「初段の重要性」
F1
(F2-1) / G1
(F3-1) / G1G2
2段目の雑音 (F2−1) は、初段の利得 G1 で割り引かれています。3段目の雑音 (F3−1) は、G1 と G2 の積でさらに大きく割り引かれます。
これが意味することは、たった一つ。
受信システム全体の雑音性能は、その初段の性能によってほぼ決定されるということです。
もし初段の利得 G1 が十分に大きければ(例えば100倍=20dB)、2段目以降の機器がどれだけうるさくても、その影響は1/100以下に抑え込まれ、無視できてしまいます。
これは単なる数式ではなく、受信機設計における絶対的な哲学です。最高の受信機を作るには、アンテナの直後に接続される初段の低雑音増幅器(LNA: Low-Noise Amplifier)に、最も低雑音で高利得な、最高性能の部品を配置することに全力を注ぐべきなのです。数億円の巨大なパラボラアンテナも、その受信性能の心臓部は、アンテナ直下に設置された指先ほどのLNAの品質にかかっているのです。
第5部 理論から実践へ:応用例と設計の勘所
理論を学んだところで、今度はそれが実際のシステム設計でどう活かされているかを見ていきましょう。
LNAの選定と受動素子の罠
フリスの公式が示す通り、LNAは受信機の感度を左右する最重要部品です。LNAを選ぶ際は、①可能な限り低い雑音指数(NF) と ②後段の影響を抑えるための高い利得(Gain) を持つ製品を選ぶことが鉄則です。
そして、もう一つ注意すべきはケーブルやフィルタなどの受動素子です。利得を持たないこれらの部品も雑音を発生させ、その雑音指数は驚くほどシンプルに関係づけられます。
NF (dB) = 損失 (Loss) (dB)
これは非常に重要な法則です。例えば、アンテナとLNAの間に3dBの損失を持つケーブルを入れたとします。このケーブルがシステムの「1段目」となり、その雑音指数は3dB、利得は-3dB (G=0.5) です。フリスの公式に当てはめると、システム全体のNFはLNA単体よりも劇的に悪化してしまいます。このため、LNAは可能な限りアンテナの直近に設置するのが設計の鉄則なのです。
衛星通信の総合評価指標:G/T (ジーオーバーティー)
衛星通信のようにシビアな世界では、受信システム全体の性能を一つの指標で表す G/T が用いられます。
- G: アンテナの利得 (信号を捉える能力)
- Tsys: 受信システム全体の等価雑音温度 (システムの静かさ)
G/Tは、受信局の「信号を捉える能力」と「システムの静かさ」を一つの数値に集約した、非常に優れた性能指標です。衛星運用者は、受信局の詳細な構成を知らなくても、G/Tの値さえ分かれば通信可能かどうかを判断できます。これは、受信局の性能を表す「通貨」のような役割を果たします。
第6部 腕試し!知識を力に変える演習問題
さあ、ここまでの知識を使って、実際の計算問題に挑戦してみましょう。
演習1:多段増幅器の総合雑音指数の計算
問題: 以下の3段増幅器を接続した。システム全体の総合雑音指数NF [dB] を求めよ。
- 1段目: 利得 10 dB, 雑音指数 1.5 dB
- 2段目: 利得 20 dB, 雑音指数 3.0 dB
- 3段目: 利得 15 dB, 雑音指数 6.0 dB
▼ クリックして解法を見る
1. 全ての値を真数に変換する
- G₁ = 1010/10 = 10
- F₁ = 101.5/10 ≈ 1.413
- G₂ = 1020/10 = 100
- F₂ = 103.0/10 ≈ 1.995
- G₃ = 1015/10 ≈ 31.62
- F₃ = 106.0/10 ≈ 3.981
2. フリスの雑音公式を適用する
Ftotal = F₁ + (F₂−1)/G₁ + (F₃−1)/(G₁G₂)
Ftotal = 1.413 + (1.995−1)/10 + (3.981−1)/(10×100)
Ftotal = 1.413 + 0.0995 + 0.002981 ≈ 1.515
3. 総合雑音係数をデシベル(雑音指数)に変換する
NFtotal = 10log₁₀(1.515) ≈ 1.80 dB
答え: 総合雑音指数は 約1.80 dB となります。初段のNF 1.5dBに非常に近い値になっており、2段目以降の影響が初段の利得によって大幅に低減されていることが分かります。
演習2:システム雑音温度の算出
問題: 雑音温度 30K のアンテナ、損失 1.0dB の給電線、雑音指数 0.8dB のLNAで構成される受信システムがある。給電線の物理温度は290Kとする。LNA入力端から見たシステム全体の等価雑音温度 Tsys [K] を求めよ。
▼ クリックして解法を見る
1. 給電線とLNAのパラメータを真数に変換する
- 給電線の損失 L = 101.0/10 ≈ 1.259
- LNAの雑音係数 FLNA = 100.8/10 ≈ 1.202
2. 各コンポーネントの雑音温度を計算する
- LNAの等価雑音温度:
TLNA = (FLNA−1)T₀ = (1.202−1) × 290 ≈ 58.6 K - 給電線の等価雑音温度:
Tfeed = (L−1)Tphys = (1.259−1) × 290 ≈ 75.1 K
3. システム全体の等価雑音温度を計算する
Tsysは、アンテナ雑音が給電線で減衰したものに、給電線自身の雑音とLNAの雑音を加えたものになります。
Tsys = Tant/L + Tfeed + TLNA
Tsys = 30/1.259 + 75.1 + 58.6
Tsys ≈ 23.8 + 75.1 + 58.6 = 157.5 K
答え: システム全体の等価雑音温度は 約157.5 K となります。損失がわずか1.0dBの給電線でも、システム雑音温度に大きな影響を与えることがよくわかります。
たび友|サイトマップ
関連webアプリ
たび友|サイトマップ:https://tabui-tomo.com/sitemap
索友:https://kentomo.tabui-tomo.com
ピー友:https://pdftomo.tabui-tomo.com
パス友:https://passtomo.tabui-tomo.com
クリプ友:https://cryptomo.tabui-tomo.com
進数友:https://shinsutomo.tabui-tomo.com

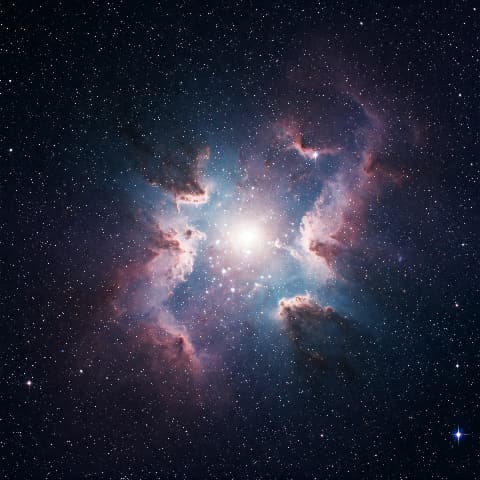
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=12673986&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0256%2F9784789830256.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=20639988&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8513%2F9784274228513_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36d703fa.cea55913.36d703fb.ef7393c7/?me_id=1213310&item_id=11508615&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7898%2F78983034.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)