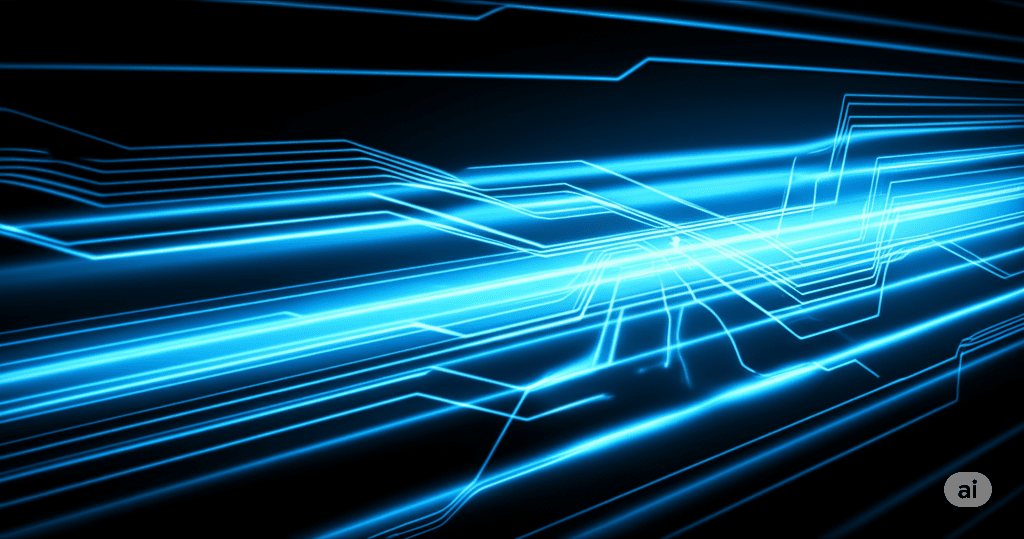電流源の仕組み
なぜ電圧が変わっても電流は一定?その謎、5分で解明します
「電圧をかければ電流が流れる。電圧が高ければ、電流も大きくなる。」
オームの法則で習った、電気の世界の常識ですよね?
しかし、もし「電圧がどんなに変わっても、流れる電流は常に一定」という、魔法のような電源があるとしたら…?
この記事で得られること 💡
- なぜ電圧が変化するのに電流が一定に保たれるのか、その謎がスッキリ解けます。
- 電流源には「2つのタイプ」があることを、明確に区別できるようになります。
- 光センサーやLED回路が、なぜあのように動作するのか、本質から理解できます。
電気の常識がひっくり返るような、エキサイティングな世界へご案内しましょう。
|
|
この記事の概要
本記事では、まず「電流源」が「電圧源」とどう違うのかという基本から解説します。次に、電流源の核心である2つのタイプ、すなわち「電圧を巧みに調整する能動的電流源」と「物理現象に支配される受動的電流源」について、豊富な例え話を交えながら、その仕組みを徹底的に解き明かしていきます。
電流源とは?電圧源との根本的な違い
まず、私たちの最も身近な電源である「電圧源」と比較してみましょう。
電圧源
乾電池やコンセントなど
- 役割
- 電圧を一定に保とうとする。
- 動作
- 接続される負荷(抵抗)によって、流れる電流が変化する。
例: 1.5Vの乾電池に豆電球(抵抗が小さい)をつなげば大きな電流が流れ、LED(抵抗が大きい)をつなげば小さな電流が流れます。
電流源
定電流回路
- 役割
- 電流を一定に保とうとする。
- 動作
- 接続される負荷(抵抗)が変わっても、流れる電流は一定。その代わり、電圧が変化する。
オームの法則 I = V / R を思い出してください。電流 I を一定に保つためには、抵抗 R の変化に合わせて、電源が自ら電圧 V を調整してあげなければなりません。
電流源とは、まさにこの「電流を一定に保つための自動電圧調整装置」なのです。
では、一体どうやってそんな器用なことをしているのでしょうか?その答えは、電流源の「タイプ」によって全く異なります。電流源の世界には、まるで性格の違う2人のシェフが存在するのです。
タイプA:調整するシェフ「能動的な電流源」の仕組み 👨🍳
1人目のシェフは、レシピ(目標電流)通りに料理を仕上げるためなら、火加減(電圧)の調整を一切惜しまない、完璧主義なシェフです。これを「能動的(アクティブ)電流源」と呼びます。
主役はトランジスタ!フィードバック制御の妙技
この能動的電流源の主役は、トランジスタという電子部品です。トランジスタは、小さな制御信号によって、大きな電流の流れをコントロールできる、電子的な蛇口のようなものです。
この仕組みを理解するために、ダムの放流システムを想像してみてください。
ダムの放流モデル (フィードバック制御)
放流量(電流)を
毎秒100トンに保つ
実際の放流量
センサーが放流量を
常にチェック
ズレがあれば水門(トランジスタ)を調整
このように、出力の結果を常に監視し、目標値からズレないように原因側を調整し続ける制御を「フィードバック制御」と呼びます。能動的電流源は、トランジスタを使ったフィードバック制御によって、負荷抵抗がどう変わろうと出力電圧を巧みに調整し、電流を一定に保っているのです。
タイプB:素材で決まるシェフ「受動的な電流源」の仕組み 🧑🌾
ここからが、多くの人が「?」となるポイントです。「トランジスタのような能動的な制御がないのに、電流源として振る舞う部品があるらしい。例えば、光センサー。あれはどういうこと?」
その答えが、2人目のシェフ、「受動的(パッシブ)電流源」です。このシェフは、調理法(電圧)を工夫するのではなく、その日に仕入れた食材(物理現象)の量で、作れる料理の量(電流)が上限として決まってしまう職人肌のシェフです。
光センサーの仕組み:回路と物理で解き明かす
フォトダイオードなどの光センサーが、この受動的電流源の代表例です。その仕組みを、「回路」と「物理」の両面から見ていきましょう。
フォトダイオードの動作原理
1. 回路の話 (逆バイアス)
外部電源(Vcc)と抵抗(R)を使い、センサーに逆向きの電圧をかけます。この抵抗Rが、センサーが生成した「電流」を、測定しやすい「電圧(V_out)」に変換する重要な役割を担います。
2. 物理の話 (電子の発生)
逆電圧により内部に「電気的な坂道(電界)」が準備されます。そこに光が当たると、そのエネルギーで電子が解放され、電界の力で坂道を一気に駆け下ります。
3. 回路と物理の連携 (電流の取り出し)
坂道を下った電子は電極から外部回路へ取り出され、抵抗Rを通って電源へ戻るループを形成します。この電子のループこそが「光電流」の正体です。p-n接合部は、発生した電子を外部へ効率よく送り出すための「仕分け通路」として機能しているのです。
もう一つの代表例:定電流ダイオード(CRD)
この受動的電流源の考え方を製品にしたのが、定電流ダイオード(CRD)です。
CRDは、内部にJFETというトランジスタを持ち、その物理的な「電流飽和特性」(ある電圧以上では電流が増えなくなる性質)を利用して、光のような外部エネルギーなしに、それ単体で一定の電流を流し続けます。
まとめ:2人のシェフを理解すれば、電流源はもう怖くない
最後に、2つの電流源の本質をもう一度確認しましょう。
能動的な電流源
調整するシェフ
- 仕組み
- フィードバック制御で能動的に電圧を調整する
- 主役
- トランジスタ、オペアンプなど
- イメージ
- ダムの水門を自動制御するシステム
- キーワード
- 調整フィードバック制御
受動的な電流源
素材で決まるシェフ
- 仕組み
- 物理現象によって電流の上限が受動的に決まる
- 主役
- フォトダイオード、定電流ダイオード(CRD)など
- イメージ
- 畑の収穫量で決まるベルトコンベア
- キーワード
- 上限飽和物理法則
|
|
たび友|サイトマップ
関連webアプリ
たび友|サイトマップ:https://tabui-tomo.com/sitemap
索友:https://kentomo.tabui-tomo.com
ピー友:https://pdftomo.tabui-tomo.com
パス友:https://passtomo.tabui-tomo.com
クリプ友:https://cryptomo.tabui-tomo.com
進数友:https://shinsutomo.tabui-tomo.com
タスク友:https://tasktomo.tabui-tomo.com
りく友:https://rikutomo.tabui-tomo.com
グリモア|プロンプト投稿共有:https://grimoire-ai.com